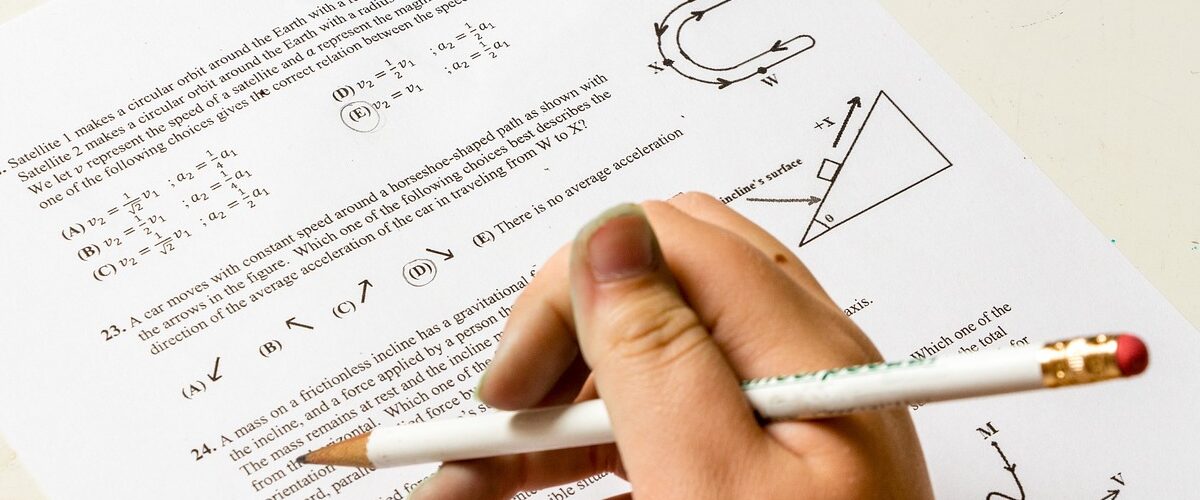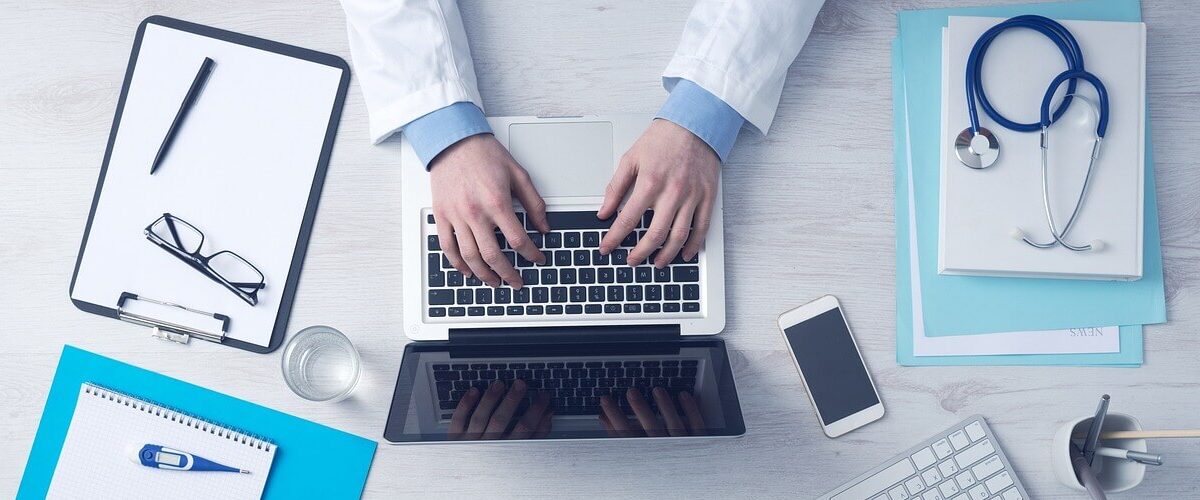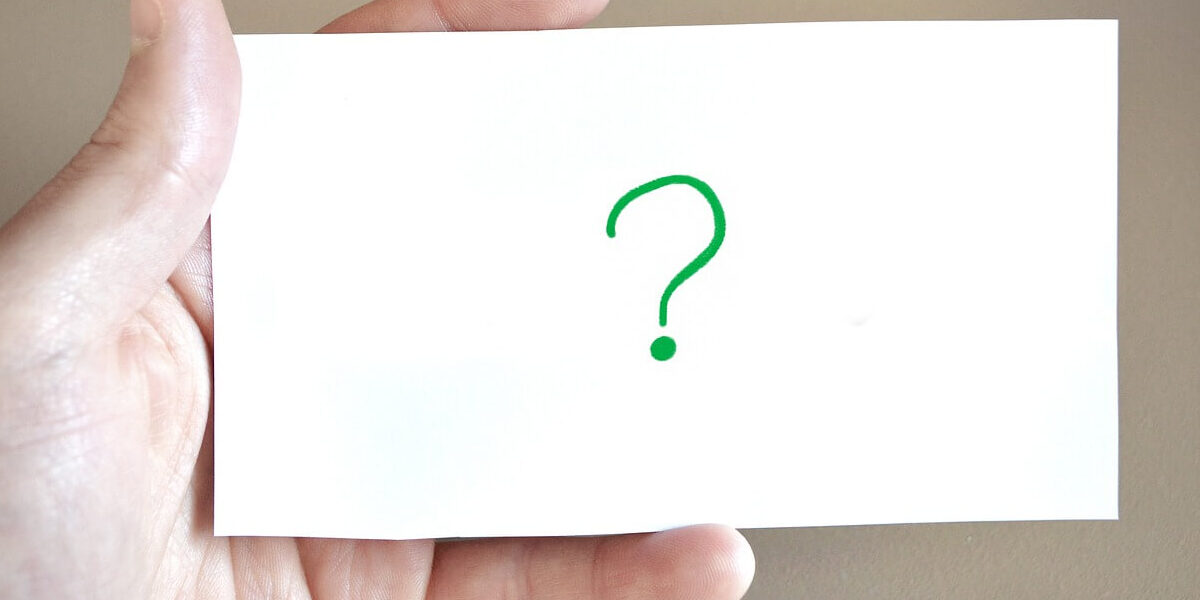【海外医学部留学】留年が当たり前?〜海外医学部で進級するには

海外医学部の進級事情と留学の可能性
みなさんは海外医学部と聞くと、入学は簡単だけれど進級、卒業が難しいというイメージを持たれている方がほとんどだと思います。
その認識は決して間違っていません。
海外医学部は多くの留学生に門戸を広げていますが、その一方で入学後に多数の試験を通して学生をふるいにかけ、進級するに相応しい学生を見極めています。
留学生のほとんどは、卒業後に自国へ帰り医師として働くことを目標としています。昨今ではヨーロッパをはじめとする多くの国々が海外から医学部留学生を受け入れています。
はじめに
ここではハンガリーの医学部を中心に話を進めていきます。
ハンガリーの医学部は現地語で学ぶ「ハンガリー語コース」と英語で学ぶことが出来る「英語コース」が存在しています。
昨今ではハンガリーの医学部へ進学する日本人が急増しています。
その背景には医学を英語で学べるという点、そして日本の厚生労働省に認定された6年制の医学部であるという点が非常に大きいと思われます。
つまり日本での熾烈な医学部受験戦争の外側(海外)から医学部へ入学し医師になれる道が存在しているということです。
先日行われた第119回医師国家試験でも、おおよそ168名もの海外医学部卒の学生が受験をしています。
受験者は年々増加傾向を辿っています。
ハンガリー医学部の進級事情
実際にハンガリーでは予備コースと呼ばれる1年間の学習期間を経て英語で学ぶことに慣れた後、医学部1年生になる方が大半を占めています。
では事実上、7年間の医学生としての生活を経て、晴れて卒業し医師として日本に帰国できる学生は実際にどのくらいの割合いるのでしょうか。
海外の医学部へ進学を考えている現役の学生、既卒生、医学部再受験を考えている方々、保護者の皆様、多くの方が1番気になるポイントと言っても過言ではないかと思います。
結論から言わせていただくと実際には4割程度の学生が、進級し卒業に達することが多いと言われています。
この4割の学生の中でもストレートに進級し、卒業に至ることが出来るのは2割程度だと言われいます。
海外の医学部では留年は珍しいことではありません。なぜならば各学年に鬼門と呼ばれる難関な科目が存在しているからです。
特に基礎医学に伴う医学部1年生、2年生、3年生は非常に多くの努力が必要となります。
また難関科目も各大学によって大きく異なります。
カリキュラムの改善による状況の変化
過去のハンガリーの医学部制度では各科目で定期試験、期末試験等の受験回数に制限があったため、途中で夢半ばにして退学(キックアウト)を余儀なくされた方も多くいらっしゃったようですが、最近は制度も見直され試験の受験回数制限は撤廃され退学させられることなく、留年し再試を受け続けることが出来るようになったようです。
またカリキュラムも改訂されたことで以前は非常に重たい科目の試験が重なってしまい手に負えないという理由で留年が絶えなかった学年もあったようですが、現在では学生の試験への負担も軽減され進級に有利になった大学も多いようです。
ハンガリー留学の可能性
これらの点を踏まえると2025年現在、より留学生ベースにアップデートされ学習環境が整ったヨーロッパのハンガリーの大学へ留学できるチャンスが到来していると言ってもいいのではないでしょうか。
昨今の円安で学費の値上がりは見られるものの学費自体は日本の国立と私立の中間程度と一般的に言われています。
またハンガリーに関しては日本人に対する政府からの奨学金制度も充実してきており、医学を学びたい、海外に挑戦したいという強い意志を持った方には検討する余地のある進学先ではないかと思われます。
以下にもう少し詳細にハンガリー医学部についてお伝えしていきたいと思います。
「ハンガリーの医学部は出席必須?〜その授業形態とは」
・レクチャー
全体講義という認識で、大きな講堂で教授1人が学生全体に講義を行います。
出席を確認する教授もいるため、出席は原則必須となります。
・セミナー
全体講義の復習、再確認のリキャップという認識で、教授または講師によって少人数クラスで授業が行われます。
欠席可能な回数が決められており、出席は原則必須となります。
・プラクティス
実験、実習がある科目で講師によって行われることが多く、グループ学習になります。
白衣等の持参が必要になることもあります。
欠席は補習対象となることが多く、他のグループに混ざっての埋め合わせが必要となります。
出席は原則必須です。
「教授によって試験の難易度が変わる?〜進級試験の形式紹介」
・筆記試験
一般的な定期試験で用いられ、日頃の成績によっては学期末試験で免除される科目(エクセプション)もあります。
選択式の問題もあれば、記述式で回答を求められる問題もあり科目により異なります。
・口頭試問
オーラル試験と呼ばれる科目担当の教授との対面式で行われれる試験で、当然のことながら英語のスピーキングスキルも必要となる試験です。
科目によってはトピックリストと呼ばれる事前に学習しておくべき内容が記載されたものが配布されることもあります。
その場でランダムでの質疑応答が行われる試験で事前準備が大切であり、科目によっては出題内容を予測するのが難しい試験になります。
ハンガリーの医学部での試験で難関とされるパートです。
・プラクティス試験
実際に行った実験、実習を再現し、それに伴う考察などを問われる実技口頭試験です。
・科目別プレゼンテーション
科目によっては授業の内容を再確認することも含めて学生各々にプレゼンテーションを課すことがあり、クラスでのセミナー(授業)中に発表する機会が設けられます。
セミナー担当の教授、講師によって評価されます。
試験全般に関して言えることですが、教授、講師によって試験で尋ねたいパート、好きな分野などが存在していることは明らかです。
日頃の授業よりそういった指導のクセを見抜き試験対策に応用することも非常に大切です。
また先輩からの情報も非常に有益で、科目によっては過去問題等も存在していることがあるので、国籍関係なく、多くの学生と交流を持つことで貴重な情報を得ることができます。
留学成功の大原則と言っても過言ではありません。
「重要なのは2年生?〜ハンガリー医学部の主な学年の流れと履修科目の例を紹介」
予備コース
予備コースは各大学が独自に開校している附属の予備コースと、外部に委託されている予備コースの2つの形態が存在しています。
附属の予備コースの学生は基本的には最終的に行われる進級試験を経て、医学部1年生へと進学していきます。
また外部の予備コースの学生は自身の行きたい大学の入学試験を独自に受験することになります。独自入試に関しては生物、化学、物理の3科目を問われることがほとんどです。
海外の医学部へ進学をする上での最初の超えるべきハードルであり、英語で何かを学ぶことに慣れる大切な期間でもあります。
高校で理系を履修していた学生には比較的有利かと思われます。
しかしながら文系出身の方も多く、英語が得意な方では学習効率が非常に高く理系出身者と遜色ない成績を出す方もいらっしゃいます。
1年生
基礎医学の初歩であり、1番つまずきやすい学年でもあります。
特に解剖学では多くの専門用語を英語で暗記する必要があり、効率的な学習が求められます。
また本格的にハンガー語を学ぶ機会が増え、後の病院実習で必要になる医療ハンガリー語の基礎を学びます。
1年次は看護研修と呼ばれる実習が夏期に課せられます。基本的に現地で行いますが、申請を行えば日本人の学生は日本で看護研修を行うことも可能なようです。
2年生
基礎医学のまとめとなる学年で、大学によっては1番留年が発生しやすい学年でもあります。
科目自体は1年次と同じものが多いですが、基礎医学のまとめとなるので非常に多い情報量での暗記を強いられます。
ここが最大の関門と言っても過言ではありません。
基礎医学は医学を学ぶ上では避けては通れないものであり、ミクロな世界の話が多く退屈に感じることも少なくないと思いますが、ここを乗り切ればいよいよ3年次より臨床医学の勉強がスタートします。
3年生
3年次になりようやく「医学」と一般的に言われるような臨床的な内容の勉強に入っていきます。
基礎医学から脱した学生としても非常に高いモチベーションで学習に励むことができます。
また一方で、基礎医学の内容を用いて学ぶ科目も多く、その典型例としては病態生理学があります。
こちらは基礎医学で学んだ生理学を応用したもので、病気の起こる仕組みを学んでいきます。
正常な状態が理解できていないと、異常な状態、すなわち病気になる理屈が理解できないことになりかねないため、非常に難しい科目で油断は禁物となります。
大学によっては3年次が難関と言われることも多く、予め大学の特色を把握しておく必要があります。
また3年次は夏期に内科研修が現地の病院で行われます。
こちらも1年次と同様に日本で行う学生も見受けられます。
4年生
3年次同様に、臨床科目中心の学年になります。薬理学という薬に関する科目が登場し、より実践的な治療に関わるような内容も増えていきます。
薬理も作用機序など薬が効く過程など非常に細かい内容を伴うため今一度、基礎医学に立ち返る必要がある場合もあります。
医学は暗記科目が非常に多いと言われますが、まさに実感する学年ではないでしょうか。
3年次同様に夏期に外科研修が現地の病院で行われます。
こちらも1年次同様に日本で行う学生も見受けられます。
5年生
5年次は座学の最終学年になります。
4年次まで乗り越えてきた学生にとっては比較的スムーズに学習を進めることが出来ると思われます。
いよいよ来年次から病院実習がスタートすると考えると身が引き締まる思いで、臨床医学のみならず、基礎医学も再度確認しておきたいところです。
また、卒業試験も控えていることを忘れず学習目標をしっかり立てる時期にしたいところです。
6年生 実習
6年次は各科のローテンションを決められた日数ずつ行っていきます。
また卒業論文の作成も並行して行っていく必要があり想像以上に慌ただしい日々になることが予想されます。
また卒業試験が行われるため、その準備も必要となります。
筆記試験と実技試験が行われるため、病院実習もしっかりと内容を理解しローテーションを回っていくことが大事になってきます。
卒業まであと一息というところなので、油断することなく最後まで走り抜けていただきたいところです。
余談にはなりますが、ハンガリーの医学部に関しては、卒業試験に合格することで卒業後にEUの医師免許が発行されます。
ヨーロッパの国々はそれぞれ独自の言語を持っている国が多く、その土地の言語が話せることがほとんどの場合条件として課せられますが、EU圏内での医師としての活動も卒業後は可能となります。
※なお、各大学や年度によって履修科目が変更される場合があります。詳細は各大学の公式ウェブサイトをご確認ください。
💡これまでざっとハンガリーの医学部について述べさせて頂きましたが、いかがだったでしょうか。
「海外の医学部は進級するのが難しい」という漠然としたものが、より具体的に理解していただけたのではないでしょうか。
世界的な進級の現状
私がここで1つ言わせて頂きたいことは、これまで上記で述べてきた学習内容は日本の医学部生も同様に学んでいるということです。
決して海外の医学部生だけが難しいことを学んでいるわけではありません。
実際に、留年に関しても日本のどこの医学部でも毎年一定数存在しているのも事実です。
日本の医学部だからストレートに卒業に漕ぎ着けられるわけではありません。
要するに医学部の進級と卒業は世界共通で難しいということです。
それらは全て個人の努力次第ということになります。
医学を学ぶということは、並々ならぬ努力が求められます。
海外医学部を選ぶ理由
ここで大事な観点としては、海外の医学部で学んでその先に何があるのか、自分自身が将来どのような医師になりたいのかという点です。
もちろん英語が得意で、海外が好きという方には非常に魅力的な環境であり、同時に卒業後は海外で医師として働く機会が得られるかもしれません。
また純日本人だけれど日本の医学部ではなく英語で医学を学んでみたい、海外に挑戦してみたい、キャリアの再挑戦をしてみたいという方にもとても魅力的な環境です。
昨今は海外医学部も医師になる1つの道として大きく認知され始めました。
東欧、中国、東南アジア、アメリカ、中南米など様々な国の医学部を卒業し、世界の各地で活躍されている日本人医師の方々、また卒業後、日本の国家試験を受験するため帰国される方々など多岐にわたる道がひらけています。
さいごに
海外医学部を志す方には、今一度ぜひご自身で問うてもらいたいです。
「自分はなぜ医師になりたいのか」、「なぜ海外に行きたいのか」、「やり遂げる覚悟はあるのか」そして「自分は将来どういう医師になりたいのか」これらの問いの答えを持って留学に臨めるかどうかが、医学留学成功の鍵になるはずです。
海外への医学留学は決して不可能な道ではありません。
正しい道筋で、正しい努力を行うことで入学、進級、卒業まで辿り着くことが出来ます。
昨今インバウンドの外国人観光客も年々増加傾向にある日本の今の時代は、医療国際化です。
日本の医学部だけではなく、広い視野で海外医学部に挑戦してみてはいかがでしょうか。
PMD海外医学部コースでは、海外医学部へのサポートを提供しています。
夢を実現する第一歩を、PMDと共に踏み出しましょう。